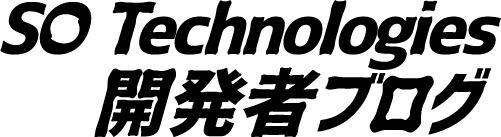はじめに
こんにちは、CTO室の伊藤です。
近年生成AIが注目を集める中、大手クラウドサービスであるGoogle CloudとAWSはそれぞれ独自の生成AIプラットフォームを提供しています。 本記事では、両プラットフォームにおけるサービスについて、特にRAGシステムやAIエージェントの開発に焦点を当てて、解説します。
両プラットフォームの生成AIサービス全体像
どちらのプラットフォームも生成AIに関連する多彩なサービスを提供していますので、まずはそれらの中から本記事のテーマに沿ったものを取り上げた上で、カテゴリ分けして整理してみます。
一部のサービスはGA時点で名称が変更されることがあるほか、サービス間で機能が重複するもの等もあり、必ずしも厳密な分類とは限らないため、現時点での参考としてご覧ください。
Google Cloud
【統合プラットフォーム】
- Vertex AI
【モデル利用(テキスト/画像/音声生成)】
- Vertex AI Model Garden
【検索】
- Vertex AI Search
【生成AIシステム開発】
- Vertex AI RAG Engine
- Vertex AI Agent Builder
【MLOps】
- Vertex AI Pipelines
AWS
【統合プラットフォーム】
- Amazon Bedrock
【検索】
- Amazon Kendra
【生成AIシステム開発】
- Amazon Bedrock Agents
- Amazon Bedrock Knowledge Bases
【MLOps】
- Amazon SageMaker
| カテゴリ | GoogleCloudの主要サービス/機能 | AWSの主要サービス/機能 |
|---|---|---|
| 統合プラットフォーム | Vertex AI | Amazon Bedrock |
| モデル利用(テキスト/画像/音声生成) | Vertex AI Model Garden | Amazon Bedrockの基盤モデル |
| 検索 | Vertex AI Search | Amazon Kendra |
| 生成AIシステム開発 | Vertex AI RAG Engine, Vertex AI Agent Builder | Amazon Bedrock Knowledge Bases, Amazon Bedrock Agents |
| MLOps | Vertex AI Pipelines | Amazon SageMaker |
Google CloudのRAG・AIエージェント開発関連機能
Vertex AIはRAGの実装を容易にするためのフレームワークとして、Vertex AI RAG Engineを提供しています。Vertex AI RAG Engineは、完全に管理されたソリューションであるVertex AI Searchと、柔軟なセットアップが可能なDIY RAGをサポートしています 。
Vertex AI SearchはGoogle 検索の品質情報検索および回答生成システムで、AIを活用した検索やレコメンデーションの機能を提供します。Google DriveやGoogle Cloud Storage等のデータソースへの接続を簡素化し、ユーザーのクエリに基づく関連情報を取得する検索APIとして、そのままRAGのリトリーバーに用いることができます。
DIY RAGについては、エンベディングやランキング等Vertex AI Searchの裏側の処理を個別のAPIで提供し、ユーザー独自の仕組みを開発可能にします。
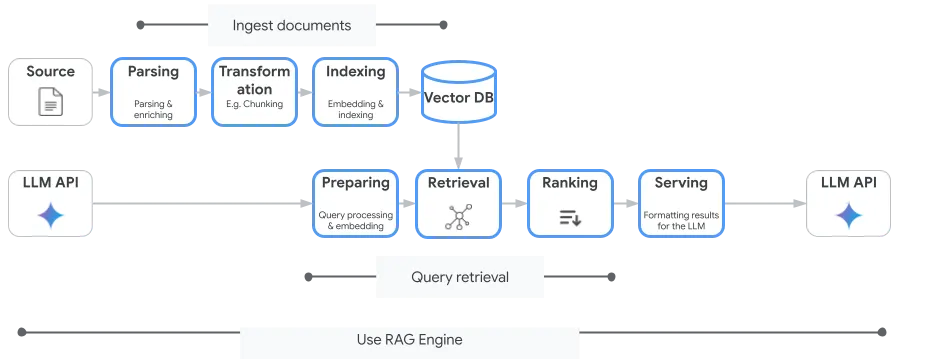 出典: Vertex AI RAG Engine の概要 | Generative AI | Google Cloud
出典: Vertex AI RAG Engine の概要 | Generative AI | Google Cloud
AIエージェントの開発アプローチとしては、Vertex AI Agent Builderが挙げられます。
Vertex AI Agent Builderは、コードをほとんど書かずに会話型や自動化AIエージェントを構築できるプラットフォームです 。上述のVertex AI Searchとも統合されており、知識を認識したAIエージェントを簡単に構築できるほか、カスタムPython関数や事前構築済みのGoogleツールを用いることで、ユーザーに代わって現実世界のアクションを実行することもできます。さらに、作成したAIエージェントはSlackやLINEと連携してWebhookで呼び出したりすることが可能です。
また、今月(2025年3月)エンジニア向けのフルマネージドサービスとして、Vertex AI Agent Engine(旧称:LangChain on Vertex AI)がGAとなりました。このサービスは、LangGraphやLangchain等のフレームワークに依存せずAI エージェントのデプロイや管理を行えるため、より本番環境での運用が容易になります。
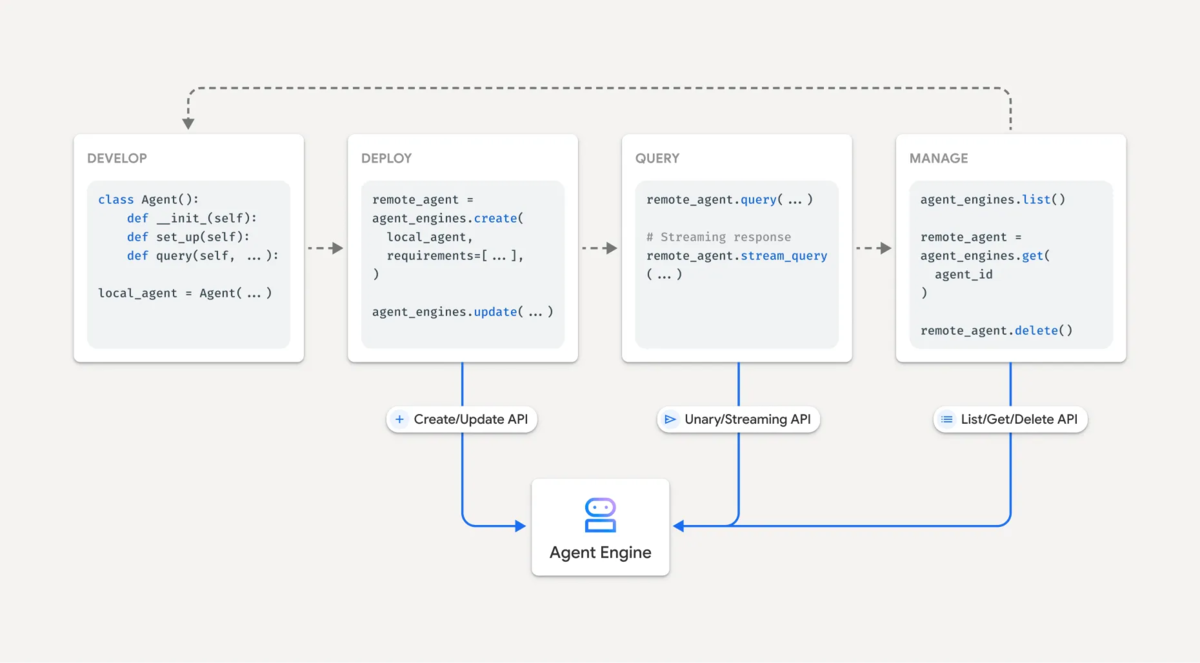 出典: Vertex AI Agent Engine の概要 | Generative AI | Google Cloud
出典: Vertex AI Agent Engine の概要 | Generative AI | Google Cloud
AWSのRAG・AIエージェント開発関連機能
AWS Bedrockの中で提供される Amazon Bedrock Knowledge Bases機能は、Amazon S3やConfluenceなどのデータソースからのデータ取り込みをサポートし、RAGに欠かせないナレッジベースの作成や管理を行う重要なコンポーネントです。また、検索システムであるAmazon Kendraや、Amazon OpenSearch Serverless、Amazon Auroraなどのベクターデータベースとも連携でき、これらを通じてVertex AI Searchと同様にRAGのリトリーバーとして活用できます。
さらに、このように構築したナレッジベースを活用し、AIエージェントの構築を行うためのサービスが Amazon Bedrock Agentsです。AWSにおいてAIエージェントの開発を担う中心的なサービスであるBedrock Agentsでは、ローコードでの開発が可能で、エージェントの目的や指示、アクション、ナレッジベースなどを設定することで、LLMによるタスクの計画から実行までを自動化できます。実行フローとしては、ユーザーのリクエストを受け取ったエージェントがタスクを解析・分解し、必要なアクションの呼び出しやナレッジベース検索を行い、最終的な回答や処理結果を生成して返します。各ステップのプロンプトは自動生成されますが、必要に応じてカスタマイズすることで、エージェントの挙動や応答品質を柔軟に制御することも可能です。
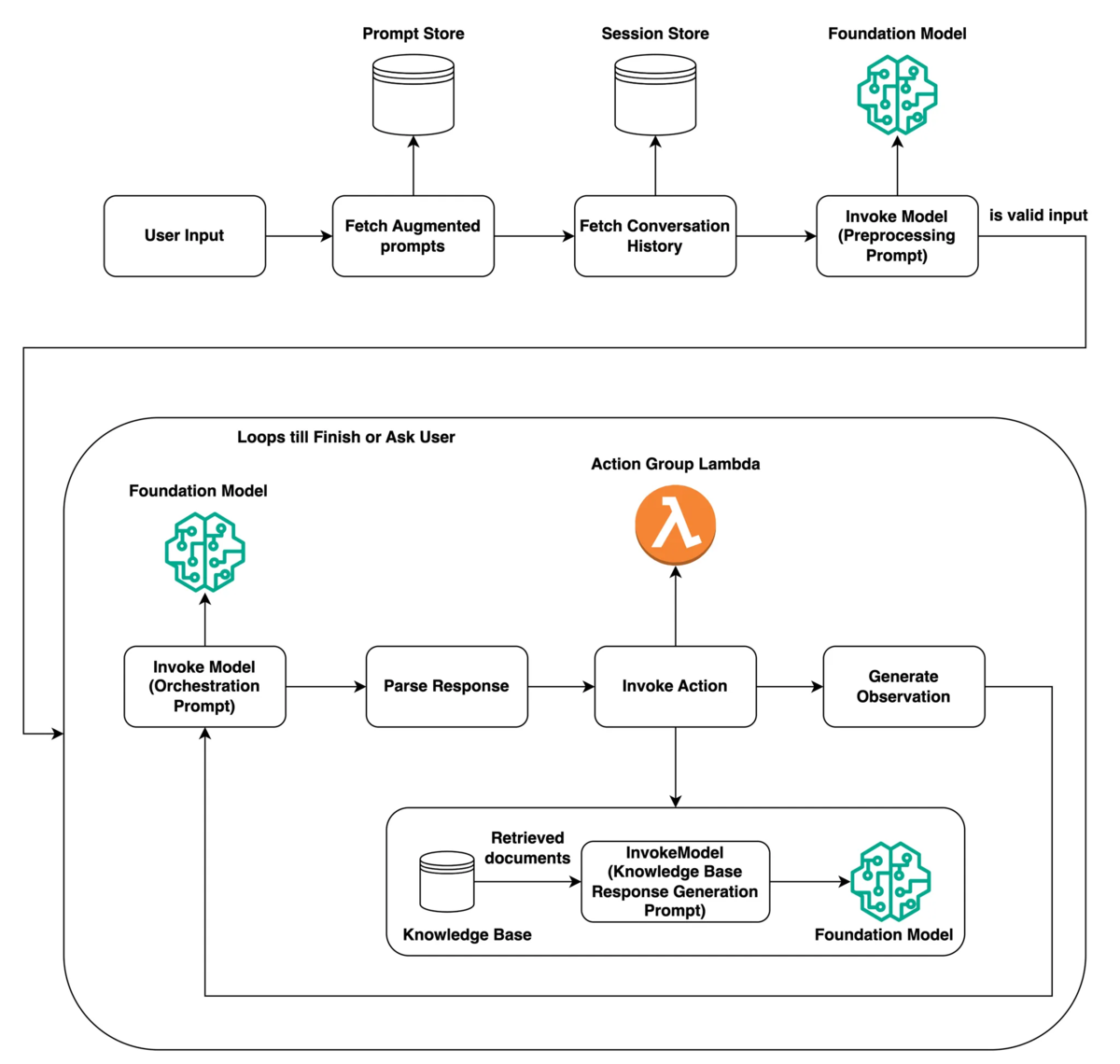 出典: AI エージェント - Amazon Bedrock のエージェント - AWS
出典: AI エージェント - Amazon Bedrock のエージェント - AWS
構成例
以上、Google CloudとAWSのサービスを紹介しましたが、実際にこれらを組み合わせてどのようにAIアプリケーションを構築するのか、両プラットフォームの例を挙げてまとめます。
例: 社内ヘルプデスクAI
Google Cloud
使用サービス: Cloud Storage、Vertex AI Search、Vertex AI Agent Builder、Google Chat
構成手順:
- データの準備: 社内ドキュメントをCloud Storageに保存します。
- データストアの作成: Vertex AI Searchを利用して、Cloud Storage内のドキュメントをインデックス化し、検索可能なデータストアを構築します。
- エージェントの設定: Vertex AI Agent Builderをデータストアに接続することで、ユーザーからの質問に対して関連ドキュメントを基に回答を生成するAIエージェントを構築できます。
AWS
使用サービス: Amazon S3、Amazon Bedrock Knowledge Bases、Amazon Bedrock Agents
構成手順:
- データの準備: 社内ドキュメントをAmazon S3バケットに保存します。
- ナレッジベースの作成: Amazon Bedrock Knowledge Basesを使用して、S3内のドキュメントを取り込み、ナレッジベースを構築します。
- エージェントの設定: Amazon Bedrock Agentsを利用し、ナレッジベースと連携するエージェントを設定します。これにより、ユーザーからの問い合わせに対して、ナレッジベースの情報を参照しながら適切な回答を生成するAIエージェントを構築できます。
このように作成したAIエージェントは、単体で完結するものではなく、実際の運用においては業務システムや自社サービスと連携させることが前提となるケースが多くあります。
Vertex AI Agent BuilderとAmazon Bedrock Agentsは、いずれもAPIエンドポイントを提供しており、社内システムやWebアプリケーションなどから直接呼び出すことで、柔軟な統合が可能です。
さらに、Google CloudではGoogle Chat、AWSではAWS Chatbotなど、他のコミュニケーションサービスと連携することで、よりスムーズに既存の業務ツールに組み込むことができます。
たとえば、SlackやTeamsなどのチャット基盤とエージェントを連携させることで、従業員が普段利用している環境から自然にAIの機能を活用できるようになります。
まとめ
今回は、Google CloudとAWSの生成AIサービスに焦点を当て、特に近年注目を集めているRAGとAIエージェントに関する機能を中心に紹介しました。
近年、生成AI関連サービスの進化は非常に速く、今回取り上げた2つのプラットフォームに限らず、次々と新機能が登場しています。私自身、各サービスの全体像を掴むのが難しく感じることも少なくありません。そのため、こうした内容を整理してみることで理解を深めたいと考えました。
この記事が、同じような感覚を持っている方にとって、サービス選定や構築の一助となれば幸いです。